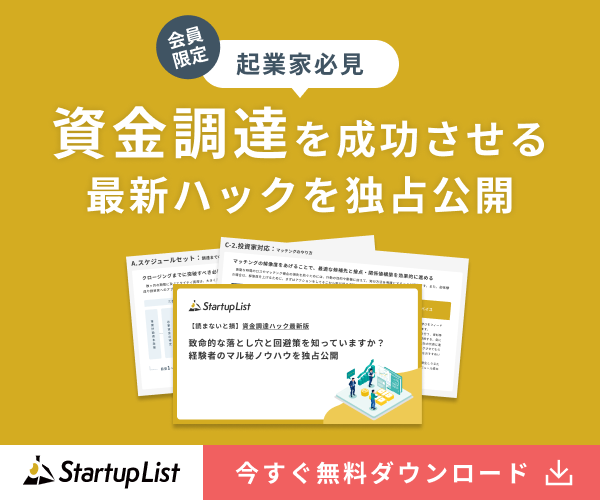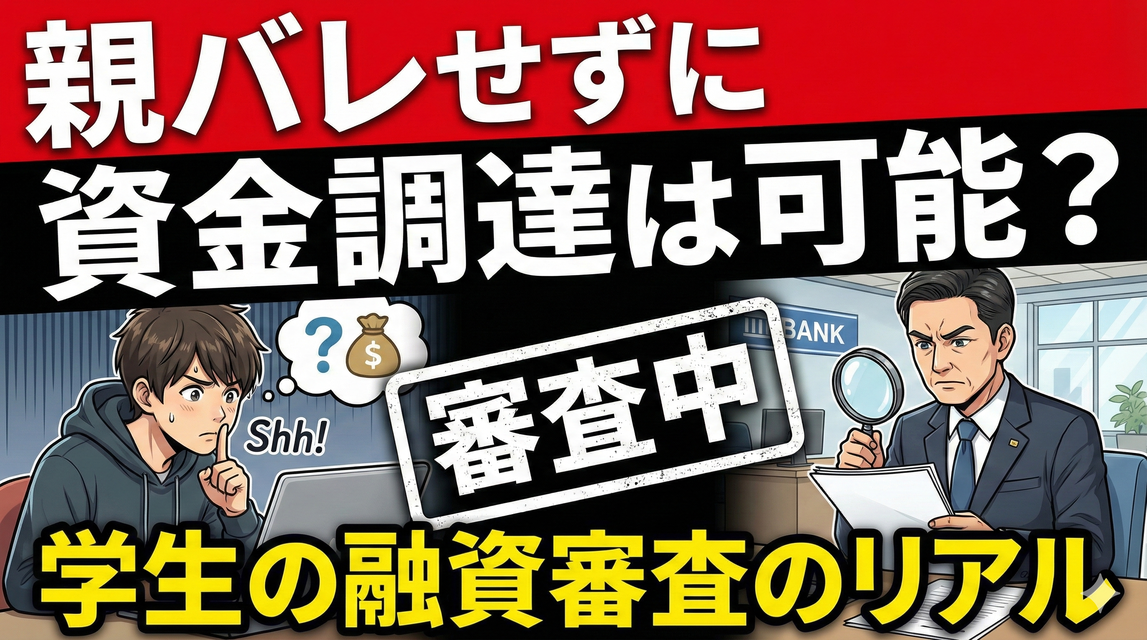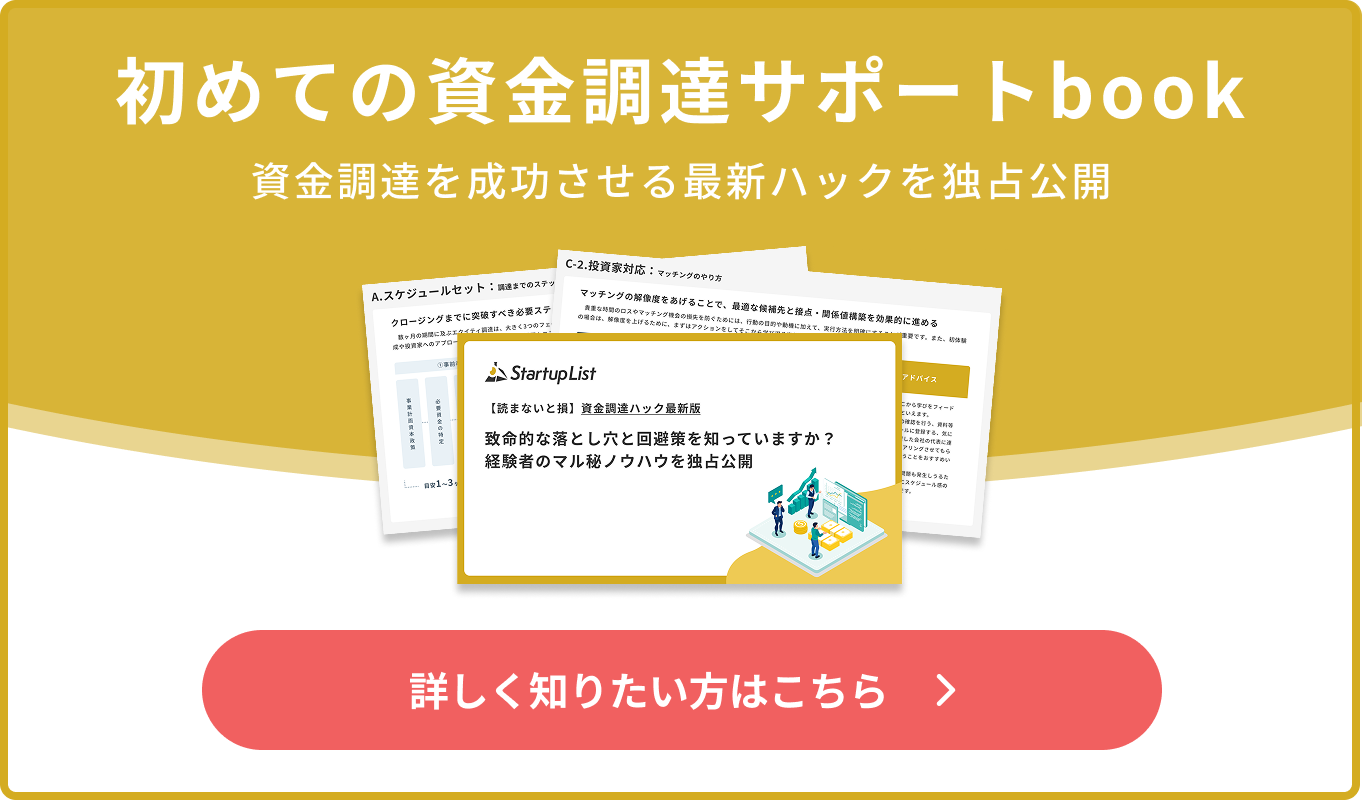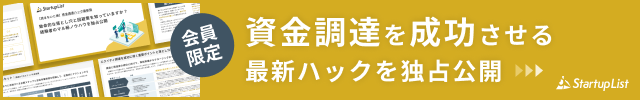この記事の監修・執筆:前川 英麿(プロトスター株式会社 代表 / 元VC)早稲田大卒業後、エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社(現、大和企業投資株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社)等でVC投資活動に従事。フロンティアターンアラウンド株式会社ではターンアラウンドマネージャーとして事業再生の現場に従事。現在はプロトスター株式会社代表取締役として、起業家支援インフラ「StartupList」を運営し、115回以上続くリアルイベント「SLピッチ」を主催。
「素晴らしいアイデアはあるが、手元にお金がない」
「借金をするのは怖いから、出資を受けてリスクを抑えたい」
起業家の多くがこうした資金調達の悩みを抱えています。しかし、断言します。実は「お金がないから起業できない」というのは誤解です。正しい知識と準備があれば、必要な資金は必ず外部から調達できます。
しかし、ネット上の「資金調達まとめ」を鵜呑みにして、フェーズに合わない調達手段を選ぶのは危険です。
なぜなら、あなたの事業モデル(スモールビジネスか、スタートアップか)や成長段階によって、「選ぶべき正解」と「絶対に選んではいけない選択肢」が明確に分かれているからです。
私は新卒でVC(ベンチャーキャピタル)の世界に入り、投資する側を経験しました。その後、フロンティア・ターンアラウンドという事業再生の専門会社で、資金調達や管理を間違えて経営破綻の危機に瀕した企業を数多く見てきました。
また現在は、StartupListとして115回以上のピッチイベント「SLピッチ」を主催し、自社(プロトスター)でも億単位の融資(デット)を活用して経営しています。
この記事では、これら「投資する側」「借りる側」「立て直す側」のすべての視点から、教科書には載っていない資金調達のリアルな最適解と、失敗しないための防衛策を、実体験を交えて徹底解説します。
0.【2026年の傾向】「金利ある世界」で変わったルール
2025年までの常識は、2026年には通用しなくなっています。最大の要因は、日本経済が完全に「金利ある世界」へと移行したこと、そして「投資家の評価軸の変化」です。資金調達に動く前に、今年特有の3つのトレンドを押さえてください。
1. デット(融資): 「借りられるだけ借りる」は自殺行為に
これまでは「低金利だから、今のうちに借りられるだけ借りてキャッシュを厚くする」が定石でした。しかし、金利が上昇局面にある2026年現在、その戦略はリスクになります。
-
変化: 変動金利の上昇により、借入金の利払い負担がボディブローのように経営を圧迫します。
-
対策: 「とりあえず借りる」ではなく、「この金利を支払っても利益が出るか(ROI)」をシビアに計算する必要があります。銀行交渉でも「金利条件」が最重要項目になります。
2. エクイティ(出資): 「夢」より「筋肉質な実業」へ
数年前までは「赤字でもいいからトップライン(売上)を伸ばせ」というJカーブ重視の投資が主流でした。しかし今は違います。
-
変化: 投資家は「いつ黒字化できるのか」を厳しく問います。また、AIがコモディティ化したため、「AIを使っています」だけでは評価されず、「AIを使ってどうやって独自のデータを囲い込むか(Moat)」が問われます。
-
対策: ユニットエコノミクス(1顧客あたりの採算性)が健全であることを証明できない限り、調達のハードルは極めて高いままです。
3. ランウェイ(生存期間): インフレによる「資金ショート」の加速
調達した資金が尽きるまでの期間(ランウェイ)の計算が狂い始めています。
-
変化: エンジニアの人件費高騰、サーバー代や広告費のインフレにより、同じ1,000万円でも、数年前より「会社が生きられる期間」が短くなっています。
-
対策: 従来の感覚で「半年持つだろう」と思っていると、4ヶ月で尽きます。見積もりを保守的にし、調達額を少し多めに設定するか、固定費を徹底的に削る覚悟が必要です。
1. 資金調達の全体像:「借りる」と「もらう」の本質的違い
資金調達の手法は多岐にわたりますが、本質的には以下の2つしかありません。この違いを腹落ちさせていないと、後で取り返しのつかない事態になります。
デット(借りる) vs エクイティ(もらう)
まずは、この2つの決定的な違いを理解しましょう。「返さなくていいからエクイティがいい」という単純な話ではありません。

【元VCの視点】
デットは「過去の信用」をお金に変える行為であり、エクイティは「未来の期待」をお金に変える行為です。
銀行は「雨が降った時(業績悪化時)に傘を取り上げる」と言われますが、VCは「雨が降った時に一緒に濡れながら傘を探してくれる(ハンズオン支援)」側面があります。ただし、その分だけ「リターン(急成長)」への圧力は強烈です。
▼自分はどっちを選ぶべき?メリット・デメリットの完全比較
出資と融資の根本的な違いとは?初心者でもわかる資金調達の基本とメリット・デメリットを徹底比較
2. 【徹底解説】資金調達7つの方法・リアル評価チャート
StartupListの現場視点で、主要な7つの手法を「難易度」「着金スピード」に加え、「経営への影響度(副作用)」で格付けしました。それぞれの「落とし穴」も併せて解説します。
① 自己資金(Bootstrapping)
-
難易度:★☆☆☆☆
-
スピード:★★★★★
-
副作用:なし(自分のお金なので)
解説と注意点:
最初の一歩です。自分の貯金を充てます。審査も契約もなく自由ですが、「全財産を突っ込む」のはNGです。
起業初期は精神的な安定が不可欠です。「生活費の半年分は残す」などデッドラインを決めましょう。ここが尽きると、目先の売上欲しさに悪い条件の仕事を受けたり、冷静な経営判断ができなくなったりします。
② 日本政策金融公庫(創業融資)
-
難易度:★★☆☆☆
-
スピード:★★★☆☆(1〜2ヶ月)
-
副作用:借入金としてBS(貸借対照表)に乗る
解説と注意点:
創業期の起業家にとって「最強の味方」です。民間銀行が相手にしてくれない時期でも、無担保・無保証人で貸してくれる「新創業融資制度」があります。金利も低く、まずはここを攻めるのが鉄則です。
ただし、面談では「夢」よりも「数字(返済計画)」が見られます。「この売上なら毎月〇万円返せます」というロジックが必要です。
▼審査通過率を上げる「創業融資」の攻略ガイドはこちら
[新創業融資制度とは?専門家に聞いた創業融資の審査ポイントと全貌]
③ 銀行融資(プロパー・保証付き)
-
難易度:★★★★☆
-
スピード:★★☆☆☆(審査長い)
-
副作用:連帯保証のリスク
解説と注意点:
ある程度の実績が出てから検討すべき手段です。最初は信用保証協会の保証付き融資から始まります。
【プロトスターの実体験:億単位のデット戦略】
弊社も創業初期は赤字を掘るスタートアップモデルでしたが、信用金庫や地銀との関係を丁寧に構築し、現在では億単位の融資枠(デット)を活用しています。
なぜあえて借金をするのか? それは「株式の希薄化(ダイリューション)を防ぐため」です。株を放出すればするほど、創業者の持分は減ります。成長資金の一部をデットで賄うことで、経営権を維持したままレバレッジを効かせることができるのです。
④ 投資家からの出資(VC・エンジェル)
-
難易度:★★★★★(狭き門)
-
スピード:★★☆☆☆(3〜6ヶ月)
-
副作用:経営権の一部喪失、Exit圧力
解説と注意点:
スタートアップの王道です。返済義務がない代わりに、急成長(Jカーブ)が求められます。「お金」だけでなく「知見」や「人脈」もセットで得られるのが特徴です。
最大の注意点は「時間のコスト」です。調達活動には半年ほどかかり、その間、社長は事業に集中できなくなります。また、断られるたびに精神を削られます。それでもなお、世界を変えるスピードを手に入れたい場合に選ぶ手段です。
【プロトスターの実体験:億単位のエクイティ戦略】
弊社もVCや事業会社かた億単位のエクイティ調達をしています。最も大事な株式を放出して得る資金です。誰に出すのか、それは非常に重要な判断です。私も複数のVCやCVCを検討し、長期的に誰にパートナーになってもらうか一生懸命考えました。特に事業会社は事業シナジーが本当に発生するのか、調達前に事業を共に立上げ、その成果も十分に判明したのちに、実行しました。エクイティはまさにお金だけの関係ではありません。
▼今のあなたに合った投資家リスト・探し方はこちら
[【2025年最新版】VC(ベンチャーキャピタル)一覧!シード向けや独立系VCを紹介]
[【2025年最新版】エンジェル投資家とのマッチングサービス5選!注意点も解説]
⑤ 補助金・助成金
-
難易度:★★★★☆(書類地獄)
-
スピード:★☆☆☆☆(入金は忘れた頃)
-
副作用:事務作業コスト
解説と注意点:
「返さなくていいお金」ですが、最大の落とし穴は「後払い」であることです。
例えば「1,000万円の補助金」に採択されたとしても、まず自腹で1,500万円(補助対象経費)を使い、その領収書を出して審査を受け、数ヶ月後にようやく入金されます。
つまり、「今お金がない人」は使えません。 これを当てにして資金繰りを組むと、立替期間中に資金ショートします。あくまで「ボーナス」として捉えてください。
⑥ クラウドファンディング
-
難易度:★★★☆☆
-
スピード:★★★☆☆
-
副作用:失敗時のレピュテーションリスク
解説と注意点:
資金調達と同時に「テストマーケティング」ができるのが強みです。BtoC(消費者向け)の商品と相性が良いです。
しかし、ページ制作や広報活動に膨大な工数がかかります。また、目標金額に届かなかった場合、「人気のない商品」というレッテルが貼られた状態で世に出ることになります。
⑦ ファクタリング
-
難易度:★★☆☆☆
-
スピード:★★★★★(最短即日)
-
副作用:高額な手数料
解説と注意点:
「入金待ちの請求書」を買い取ってもらう手法。黒字倒産を防ぐ緊急手段として有効ですが、手数料が10〜20%と高額です。
これを常用すると利益率を圧迫し、ジリ貧になります。ターンアラウンドの現場でも、ファクタリングに手を出した企業の多くは、その後かなり厳しい資金繰りに追い込まれていました。あくまで「最後の止血処置」と考えてください。
3. 「SLピッチ」115回のデータで見る:成功する調達の条件
私たちは毎月「SLピッチ」を開催し、累計数百社の起業家と投資家の対話を見てきました。そこで見えた「資金調達に成功する起業家」には、明確な共通点があります。
成功のカギは「ピッチデック(資料)」の構造にある
投資家は多忙です。1日に何件ものピッチを聞いています。最初の判断は数分のピッチや資料で行われます。
成功する企業の資料は、単なる機能説明(What)ではなく、「市場の魅力(Why Now)」や「なぜ我々か(Why Us)」が論理的に構造化されています。
【投資家が「No」と判断する瞬間ワースト3】
①市場規模が小さすぎる:「いいビジネスだけど、スモールビジネスだね(上場できないね)」と判断された瞬間。
②競合優位性がない:「Googleがやったら終わりだよね?」という質問に答えられなかった瞬間。
③解像度が低い:「仮説です」ばかりで、顧客へのヒアリングや現場検証(トラクション)の跡が見えない瞬間。
自己流で作るのではなく、「VCが評価する型(テンプレート)」に合わせて作ることが、最短での調達ルートです。
▼【テンプレ公開】SLピッチ実績から導き出した「勝てる資料」の構成
[VCを唸らせる「ピッチデック」の構成テンプレート|SLピッチ115回の実績から導き出した正解]
バリュエーション(企業価値)の高望みは失敗する
「高い株価で調達できた=成功」ではありません。ここを勘違いしている起業家は多いです。
実力以上の高い株価をつけてしまうと、次回の調達で株価が下がる「ダウンラウンド」のリスクが高まります。こうなると既存投資家との信頼関係が崩れ、最悪の場合、追加調達ができずに詰みます。
SLピッチの現場でも、「適正な相場観」を持っている起業家ほど、スムーズに投資が決まる傾向にあります。
▼あなたの適正フェーズは?ラウンドごとの相場解説
[【2025年版】シードラウンドとは?調達額の相場や株主比率、シリーズAへの進み方を徹底解説]
4. 元事業再生担当が見た「黒字倒産」の恐怖と回避策
私がフロンティア・ターンアラウンド時代に見てきた「経営危機に陥る企業」の共通点は、契約書の不備などではありません。もっと根本的な「お金の流れ(資金繰り)」の軽視です。
ここでは、実際に起きうる「失敗のリアル」をお話しします。
ケーススタディ:黒字なのに会社が死ぬとき
あるIT開発会社(A社)の話です。A社は大型案件を受注し、帳簿上の売上は急拡大していました。社長は「これで安泰だ」と喜び、人員を倍増させ、オフィスも移転しました。
しかし、その大型案件の入金は「検収完了の翌月末」。開発トラブルで検収が2ヶ月遅れ、入金はさらに先へ。
一方で、倍増させた社員の給与支払いは毎月やってきます。家賃も待ってくれません。
結果、A社は「PL(損益計算書)上は数千万円の黒字」だったにもかかわらず、手元の現金(キャッシュ)が底をつき、倒産しました。 これが「黒字倒産」です。
「売上」ではなく「資金繰り表」を見ろ
JAL再生の際、稲盛和夫氏が真っ先に徹底させたのも、精緻な「資金繰り表」の管理でした。
再生の現場では「PL(損益)は意見にすぎないが、CF(キャッシュフロー)は事実である」と言われます。
どんなに素晴らしいビジョンがあっても、現金が1円でも足りなくなれば、その瞬間にゲームオーバーです。
無理な借入は「死期の先送り」にすぎない
「借りられるだけ借りておこう」という考えも危険です。明確な返済計画(どうやって利益を出して現金を残すか)がない借入は、問題を先送りしているだけです。
借入金は、事業がうまくいかなければ、毎月の固定費(返済)として重くのしかかり、最終的に資金繰りを圧迫して首を絞めます。
「資金ショート=即死」。
この事実を直視し、まずは精緻な資金繰り表を作ること。これが、あなたの会社を破綻から守る唯一の防具です。
5. 【目的別】フェーズ別・資金調達の最適解ルート
失敗を避けるためには、事業フェーズに合った適切な調達手段を選ぶ必要があります。StartupListで推奨している「フェーズ別の勝ち筋」を整理します。
フェーズ1:創業準備〜直後(シード期)
-
状態:アイデアのみ、または試作品レベル。売上なし。
-
正解ルート:
-
自己資金で会社設立。
-
日本政策金融公庫(新創業融資)で数百万円を確保。ここで得た資金でプロトタイプを作る。
-
(急成長モデルなら)エンジェル投資家へアプローチし、シードマネーを得る。
-
フェーズ2:事業開始〜成長初期(アーリー期)
-
状態:プロダクトが完成し、PMFの兆しが見えた(顧客がつき始めた)。
-
正解ルート:
-
VC(ベンチャーキャピタル)からの本格的な出資調達。数千万〜数億円を入れ、マーケティングを踏む。
-
信用金庫・地銀との付き合いを開始。少額でもいいので「借りて、返す」実績を作り、銀行からの信用スコアを貯める。
-
フェーズ3:急成長・拡大期(ミドル・レイター期)
-
状態:売上が安定拡大中。IPOが見えてきた。
-
正解ルート:
-
大型のVC調達に加え、銀行からのデットファイナンス(融資)枠を拡大。
-
ハイブリッドな調達で、株式の希薄化を防ぎつつ、レバレッジを効かせる。プロトスターが現在行っているのもこのフェーズの戦略です。
-
6. 初心者がハマる「資金調達の落とし穴」Q&A
Q. 契約書が難しくて…読まなくても大丈夫?
A. 絶対にダメです。
特にVCからの出資では「優先株(種類株)」が一般的です。ここには「清算優先権」などの条項が含まれることがあります。
これは倒産に直結するわけではありませんが、条件によっては**「会社を10億円で売却したのに、優先権を持つ投資家が利益を総取りし、創業者には1円も残らなかった」**という悲劇を招きます。Exit時の果実に関わる重要な点なので、必ず専門家に相談してください。
Q. 投資家なら誰でもいいですか?
A. 「お金に色はついています」。
価値観の合わない投資家を入れると、後で経営方針の違いで揉め、解任動議を出されることもあります。出資は「結婚」と同じくらい、相性が重要です。
StartupListでは、投資家の専門領域や過去の投資先が見えるため、こうしたミスマッチを事前に防ぐことができます。
自社に合ったVC・投資家を効率的に見つけませんか?

StartupListでは、投資家の投資レンジや評価基準、
過去の経歴等から自社に合った投資家を検索可能です。
StartupList上で、見つけた投資家とそのままコンタクトできます。
現在、登録済のベンチャー企業は8,500社以上、投資家数は3,700名以上。
まとめ:資金調達は「お金集め」ではなく「仲間集め」
資金調達とは、単にお金を得る行為ではありません。
あなたのビジョンに共感し、「この船に乗せろ」と言ってくれる応援団(ステークホルダー)を増やすプロセスです。
デットであれば「銀行」という堅実なパートナーを。
エクイティであれば「投資家」というリスクテイカーなパートナーを。
それぞれの特性を理解し、今の自分に最適なパートナーを選んでください。
まずは、自分の事業がどのフェーズにあり、誰を仲間にすべきかを見極めることから始めましょう。
監修者情報

関連記事
- ベンチャー企業の資金調達方法!デッドとエクイティどう使い分ける?
- エンジェル投資家とは?投資を受けるメリットと探し方
- 新創業融資制度とは?審査ポイントや全貌を取材
- 出資と融資の根本的な違いとは?初心者でもわかる資金調達の基本とメリット・デメリットを徹底比較